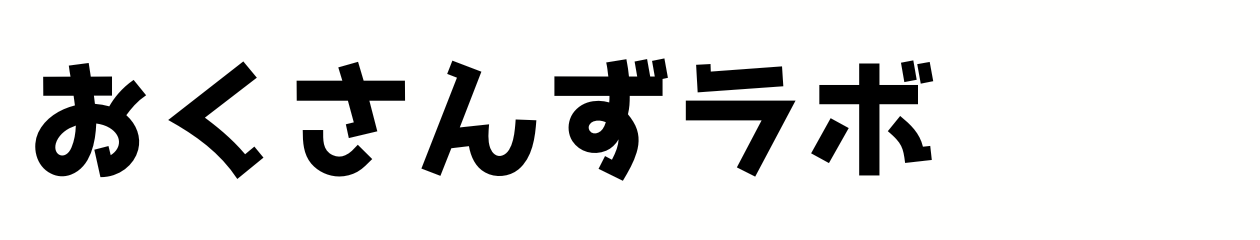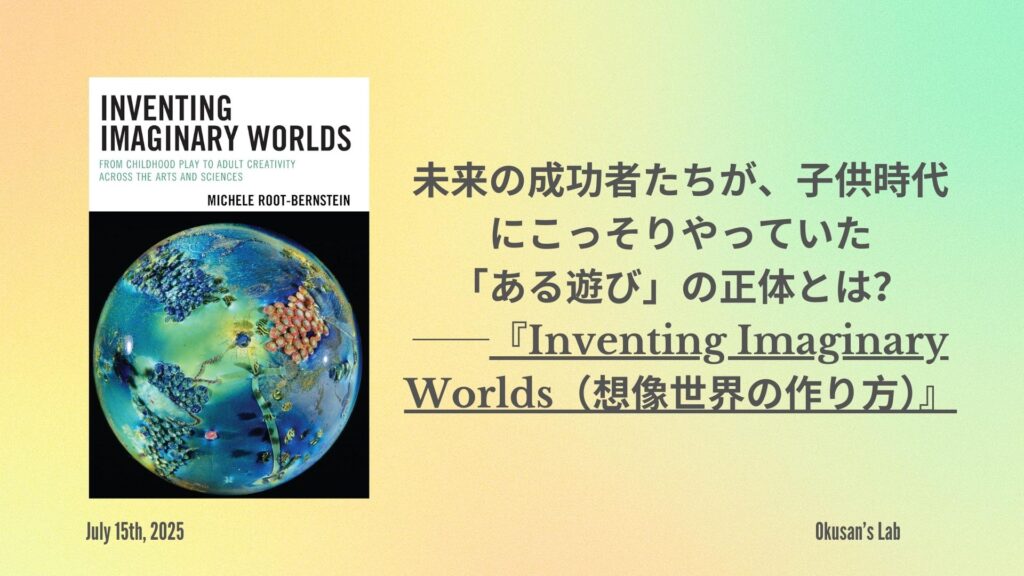
『Inventing Imaginary Worlds(想像世界の作り方)』って本を読みました。著者はミシェル・ルート=バーンスタインさんで、歴史家でありながら創造性研究の専門家、しかも現役のアーティストでもあるという、なかなかユニークな経歴の持ち主です。
で、この本の主題は、もうタイトルそのまんまですが、「子供の頃にどれだけ精巧な『空想の世界』で遊んだかが、大人になってからの創造性、特に天才的なレベルのひらめきと深く関わっている」って話。しかも、これは小説家やアーティストだけの話じゃない、と。科学者、哲学者、起業家まで、あらゆる分野の天才に共通するっていうんだから、穏やかじゃないですよね。
「うちの子、一日中なんかブツブツ言いながら空想のキャラと戦ってるけど、大丈夫かしら…」なんて心配が、「もしかしてこの子、将来ノーベル賞獲るんじゃね?」って期待に変わるかもしれない。そんな一冊でございました。
ということで、以下、印象に残ったポイントをまとめておきます。
天才は「空想世界」で遊んだ確率が2倍以上高い
まず、この本のキモになるのが、著者たちが実施した調査の結果。彼らは「天才助成金」とも呼ばれるマッカーサー・フェロー(各分野の超クリエイティブな人たち)と、普通の大学生を比較。比較の内容は、「子供時代に、自分だけのオリジナルな世界(パラコスム)を作って遊んでましたか?」って質問です。
結果はどうだったかといえば、
- なんと、マッカーサー・フェローは、一般学生に比べて2倍以上も「空想世界で遊んだ」経験を持つ割合が高かった!(フェロー26% vs 学生12%)
んだそう。しかも、その内訳がまた面白くて、この傾向は、芸術や人文科学の分野だけじゃなく、科学分野でも、社会科学でも、全部の分野でクッキリと差が出たらしい。ブロンテ姉妹が『ゴンダル』っていう空想の国で遊んでたとか、トールキンが『中つ国』を作ったって話は有名ですけど、実は哲学者のニーチェも、物理学者のデイヴィッド・リーも、神経学者のオリバー・サックスも、みんな子供時代は熱心な「ワールドプレイヤー」だった、と。
つまり、子供の空想遊びは、物語を作る練習なんかじゃなくて、分野を問わない「問題解決能力」と「システム思考」の筋トレだになっているのではないか、と。
なぜ「空想ごっこ」が脳を鍛えるのか?
じゃあ、なんでそんな遊びが天才性を育むのか? 本書によれば、空想世界ごっこ(ワールドプレイ)は、最高の「学習の実験室」だからじゃないか、と説明しています。
例えば、著者の娘さんが作った「カーランド」という世界。この世界の住人は「金属を使えない」っていう縛りプレイを自らに課したらしい。そうすると、「じゃあ、鍋や道具はどうやって作る?」「家はどう建てる?」って感じで、創造的な問題解決をせざるを得なくなる。これが、現実世界で失敗のコストなしに、仮説検証を繰り返す究極のシミュレーションになっているのだ、ってことですね。
さらに、この遊びは、ルート=バーンスタイン夫妻が提唱する「13の思考の道具」を、自然に、しかも統合的に鍛え上げる最高のトレーニングになっているのではないかと説明されています。つまり、
- 観察する力: 現実世界をじっくり見て、空想世界の材料にする。
- 抽象化する力: 地図を描いたり、法律を作ったりする。
- モデリングする力: 世界の模型やシステムを構築する。
- 共感する力: 自分が作ったキャラクターの気持ちになってみる。
これらを、学校の授業みたいにバラバラに学ぶのではなく、子供は遊びに夢中になる中で、全部ごちゃ混ぜにして使いこなしていく。空想世界という壮大なプロジェクトを回すために、脳のあらゆる機能を総動員するわけです。そりゃ、賢くなりますわなぁ。
現代社会が、静かに「天才の芽」を摘んでいるという悪夢
で、ここからがさらに考えさせられる話。この、未来のイノベーターを育む上で超重要な「ワールドプレイ」が、現代社会では絶滅の危機に瀕しているって話にも触れられています。
原因はハッキリしていて、
- 構造化されすぎた子供の時間: 塾だ、習い事だと、子供から「何もしない自由な時間」が奪われている。
- 消費型のエンタメ: 自分で世界を作る代わりに、完成されたビデオゲームやキャラクターグッズを「消費」する遊びが主流になっている。
- 「遊びは無駄」という風潮: 特に大人が「遊ぶ」ことへの罪悪感が強い。
要するに私たちが良かれと思ってやってる「教育」や、与えている「娯楽」が、実は子供の才能の芽を根こそぎ摘んでるんじゃないかっていう、かなり皮肉な話ですね。既製品の世界を探検するのは楽しいかもしれないけど、それは「消費者」の訓練であって、「創造者」の訓練にはならない。著者は「自分で創造できるという可能性そのものを断ち切ってしまう」とまで言っていたりします。これは耳が痛い…。
とはいえ、本書でも別に「ゲームは全部悪だ!」なんて言っているわけではありません。問題は「消費か、創造か」という点。例えば『マインクラフト』みたいに、ツールだけが提供されて「さあ、あとは好きに作れ」というサンドボックス型のゲームは、現代における最高のワールドプレイの舞台になり得る、と。要は、受け身になるか、能動的になるか。その違いですね。
じゃあ、どうすればいいのか?
本書では、親や教育者ができることも具体的に示されています。それは別に難しいことじゃなくて、
- 「何もしない時間」を死守する: とにかく、子供に退屈する時間を与える。これが全ての始まり。
- 「散らかってもOK」な環境を作る: 段ボール、粘土、布切れ、ブロックみたいな、どうにでもなる「余白」のある素材を与える。完成品のおもちゃより、よっぽど創造性を刺激する。
- 答えのない問いを投げかける: 「そのお人形さん、夜になったらどこ行くんだろうね?」みたいに、子供の想像力に火をつけるような質問をして、あとは黙って見てる。親が介入しすぎないのがコツ。
ということで、本書は、単なる子育て本や教育論に留まらない、「我々の社会は、イノベーションの源泉を自ら枯渇させているのではないか?」という、巨大な問いを突きつけてくる一冊でございました。
読了後には、想像力って、現実から逃げるための「ファンタジー」じゃないんだよなーと改めて感じたりしましたね。むしろ、現実をより良く作り変えるための「シミュレーション装置」なのじゃないかと。子供たちが無心に空想の世界をこねくり回している時、彼らは実は、未来の世界をデザインするための、最も重要で根源的な訓練をしているのかもしれません。
私たちが「無駄だ」と切り捨ててきたものの中にこそ、未来を切り拓く鍵が眠っている。そんなことを痛感させられる一冊でした。おすすめ。