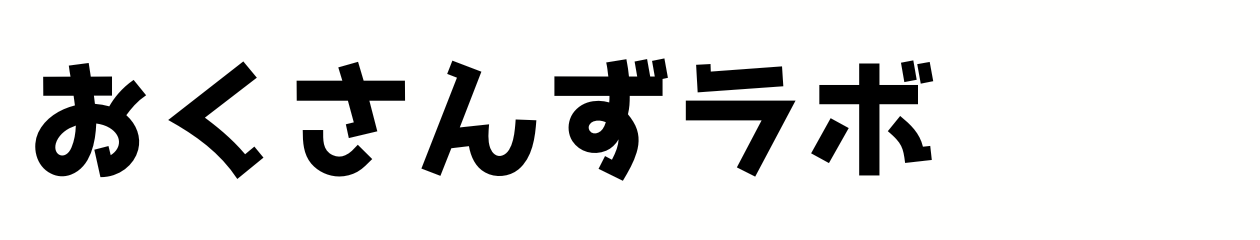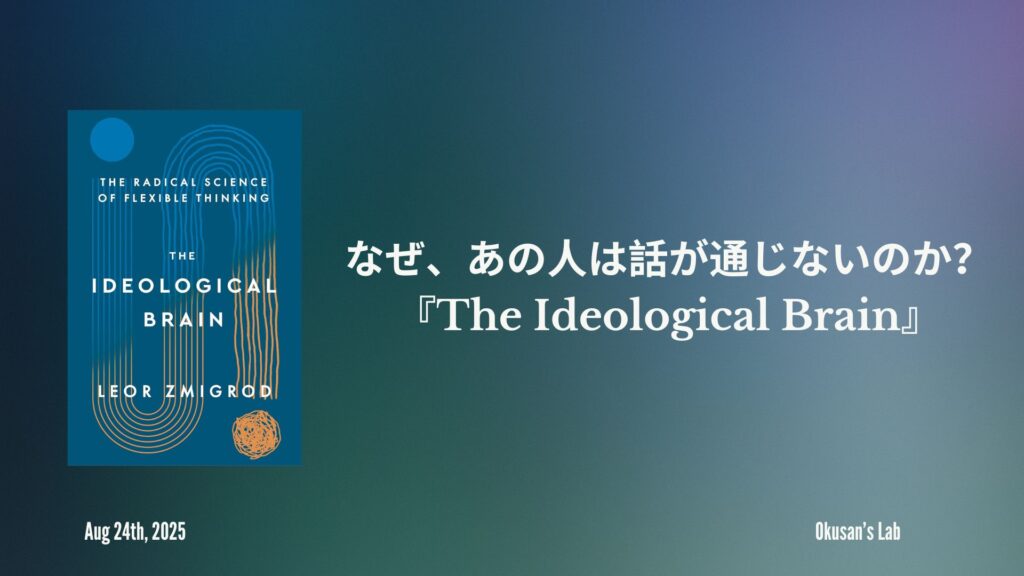
今週は『The Ideological Brain』って本を読みました。こちらはケンブリッジ大学の神経科学者であるレオール・ズミグロッド先生が書いた一冊でして、ひとことで言うと「政治的な対立や過激思想って、実は脳の“柔軟性”の問題なんじゃないの?」ってのを、データでゴリゴリに論証していく本になります。つまり、「なぜ人は過激化するのか?」「なぜ特定の思想にガチガチに固執する人がいるのか?」といった問いに対して、それってその人の思想(右翼とか左翼とか)の“中身”にあるんじゃなくて、情報を処理する脳の“スタイル”、つまり「認知的硬直性」にあるんだってのを示してくれているわけですね。個人的には、こういった社会的な問題を科学でバッサリ斬るアプローチはかなり好物なので、非常に楽しく読ませていただきました。
まず、本書のキモになるのが「認知的硬直性」って概念です。平たく言うと、「新しいルールに適応したり、新しい証拠を見て考えを変えたりするのがどれだけ苦手か」ってこと。ズミグロッド博士に言わせれば、政治的に過激な人ってのは、右だろうが左だろうが、この「脳のカタさ」が共通して高い傾向にあるらしい。
これは、政治思想の「蹄鉄理論(horseshoe theory)」を裏付ける話だととも説明されています。つまり、政治思想ってのは一直線の右から左じゃなくて、U字磁石(蹄鉄)みたいに、極右と極左は穏健派より、むしろ心理的に似通っているのではないかと。信じてる“モノ”は真逆でも、信じ方の“スタイル”は同じ。つまり、「敵は○○だ!」と叫ぶAさんと、「敵は××だ!」と叫ぶBさんは、脳のOSレベルではソックリさんかもしれないってことですね。これは普段の論争を見てても納得できるケースが少なくないんじゃないでしょうか。
ちなみに、その「脳のカタさ」ってどうやって測るの?って話ですが、ここで出てくるのが「ウィスコンシン・カード分類課題(WCST)」っていう、(なんとも地味な)心理学テスト。具体的には、
・PCの画面にカードが出てきて、被験者はそれを「色」「形」「数」のどれかのルールに従って分類する。
・正解のルールは教えてもらえず、フィードバックだけで探り当てるしかない。
・で、慣れてきた頃に、いきなり何の予告もなく正解ルールが「色」から「形」に変わる。
このテストで一番見たいのは、ルールが変わった後、どれだけ前のルール(=もはや間違い)に固執しちゃうか(保続エラー)。前のルールに従い続ける人ほど「頭がかたい」認定されるわけですね。
で、ここからが本題で、このただのカードゲームでエラーを連発する人ほど、現実世界でも教条的で、自分の信念をなかなか変えられない傾向があった、ということが繰り返し確認されているんだそう。複雑そうに見える政治的スタンスが、こんな単純なゲームの成績で予測されちゃうかもしれないわけですね。我々の“高尚な”イデオロギーってのは、実は脳の知覚的なクセと地続きだった、って感じですね。
じゃあ、なんで私たちはそんなにイデオロギーに惹きつけられるのか。博士によれば、イデオロギーは複雑でワケのわからん世界を理解するための「認知的ショートカット」なんだそうな。脳は基本的にナマケモノで、不確実性をめちゃくちゃ嫌う。そこに「答えはこれだ!」「こう考えれば全部スッキリするぞ!」っていうイデオロギーが提示されたら、そりゃ飛びつきたくもなりますわな(この辺は先日ブログにもまとめた「A trick of the mind」に近いところも感じましたね)。
このショートカットには副作用があって、一度そのOSをインストールすると、脳が物理的に再配線されてしまう。新しい情報に鈍感になり、適応力が下がり、白黒つけないと気が済まなくなる。これはもう、ただの「意見」じゃなくて、脳の構造変化なわけです。おそろしや。。
とはいえ、絶望で終わらないところが本書のいいところ。救いとして本ブログやNoteではおなじみの「神経可塑性」が提示されています。脳は筋肉と同じで、鍛えれば変わる。ズミグロッド博士は、「脳のストレッチ」として以下のような考え方をしてみることを提案しておられます。
・あえて白黒つけずに、グレーな状態に耐えてみる
・意識的に、自分と真逆の立場の人の視点に立ってみる
・「常識」や「当たり前」を疑うクセをつける
こういったトレーニングで、私たちは自分の「イデオロギー脳」の呪縛から、少しずつ自由になれるかもしれない、と。
個人的に本書を読んでいて感じたのは、この「認知的硬直性」って話は決して政治思想だけの話じゃないよなーってところ。例えば、このアイデアはまんま会社組織の話しにも置き換えられるはずで、
・「昔からこうやってきたから」と言って、新しいやり方をガンとして受け入れないベテラン
・一度成功したビジネスモデルに固執して、市場の変化に対応できずに沈んでいく企業
・「ウチの部署のやり方が絶対だ」と信じて、他部署と対立するセクショナリズム
といった感じで、これらは総じて、個人の脳の「硬直性」が、組織全体の「イデオロギー脳」にまで発展しちゃったケースともとらえられるはず。問題は「右か左か」じゃなくて、「カタいか、やわらかいか」。この視点を持つだけで、普段の仕事の景色もちょっと違って見えてくるかもしれませんな。
結局のところ、本書が言ってるのは、「本当の敵は、意見が違う“誰か”じゃない。自分の中にも潜んでいる“思考のカタさ”そのものだ」ってことなんでしょう。自分の脳の「バグ」を自覚して、意識的にハックし続ける。それこそが、このクソ面倒くさい社会を生き抜くための、最強の武器になるのかもしれないなー、と。