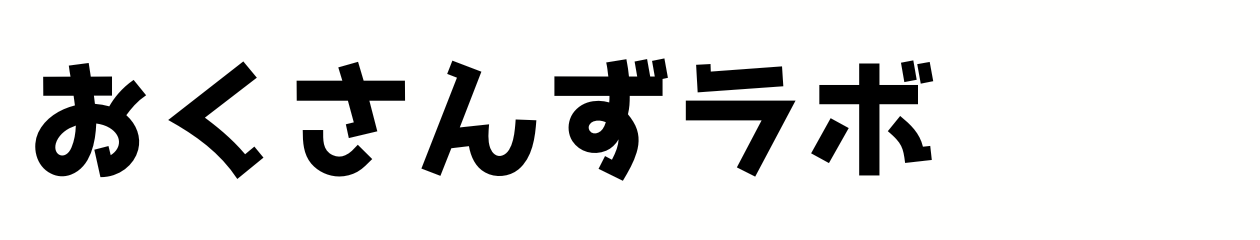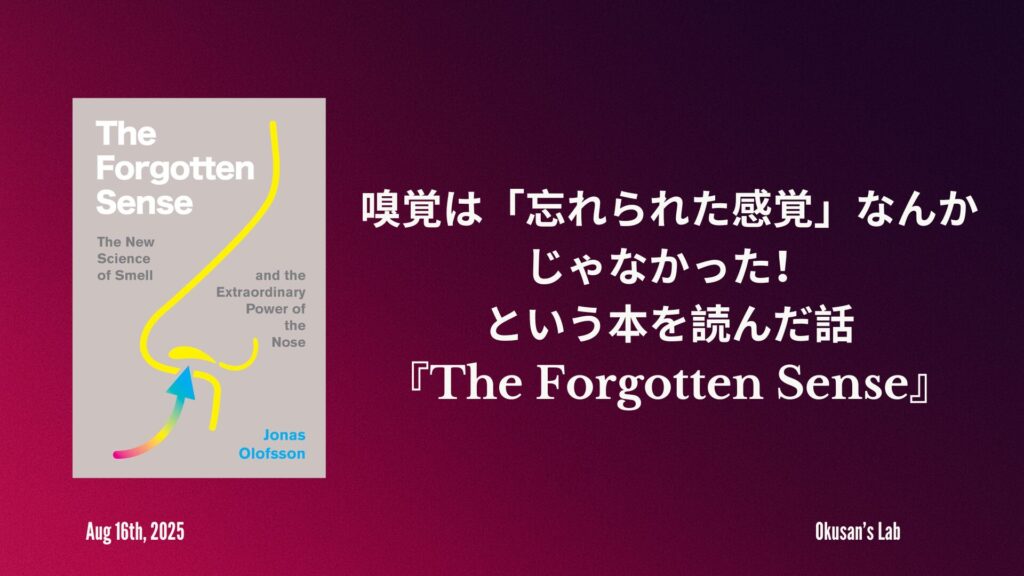
『忘れられた感覚(The Forgotten Sense)』って本を読みました。著者はヨナス・オロフソン博士、嗅覚研究の第一人者でして、この分野の最新の知見をこれでもかと詰め込んだ一冊になっておりました。この本の主張を一言でいうなら、「あなたの人生の質、人間関係、さらには健康寿命まで、その鼻が握っているぞ!」って感じ。読了後は、自分の鼻がいかにサボってたか、どれだけのポテンシャルを秘めていたかを思い知らされました。
まず大前提として、私たちが「人間の嗅覚は犬に比べて劣ってる」と思い込んできたのは、完全に濡れ衣だったって話から面白いです。もともとは19世紀の学者たちが「人間は理性の生き物だから、獣的な嗅覚は退化したのだ」みたいな俗説を広めたのが起源だったそうなんですが、オロフソン博士によれば、生物学的なハードウェアの問題じゃなく、単に私たちが嗅覚に対する「注目と知識」を萎縮させてきただけなんだ、と。つまり、サボってただけで、本来のスペックはめちゃくちゃ高いというわけですな。
嗅覚の何がそんなに特殊なのか? それは、脳への情報の伝わり方にあります。視覚や聴覚の情報が、脳の「総合受付(視床)」を通ってから各部署に回されるのに対し、嗅覚だけは例外。匂いの信号は受付をスルーして、感情を司る「扁桃体」や記憶の製造工場である「海馬」に直接ブッ刺さるVIPパスを持ってるわけです。
- 嗅覚: 匂い分子 → 鼻 → (直通) → 感情・記憶の中枢
- 他の感覚: 映像・音声 → 目・耳 → 脳の総合受付 → 感情・記憶の中枢
この「脳の裏口ルート」こそが、特定の匂いを嗅いだ瞬間に、昔の記憶が鮮明な感情と共に蘇る「プルースト効果」の正体。嗅覚は単なる情報センサーじゃなく、過去に一瞬でワープできる「感情のタイムマシン」なんだ、と。
さらに面白いのが、「匂いを嗅ぐ」という行為が、実はめちゃくちゃ知的なトップダウン処理だという点。私たちは鼻先で分子をキャッチしてるだけだと思いがちですが、これがまた大間違い。脳が過去の記憶や文脈、期待値なんかを総動員して、「これはたぶん、あの匂いだろう」と結論を押し付けているに過ぎない。これは「A trick of the mind」にも通ずるところがありますね。
その証拠に、多くの人が「匂いはわかるけど名前が出てこない」って経験をしますよね。あれは鼻が悪いんじゃなくて、脳が「名前を特定するより、他の情報と統合するのを優先するぜ!」っていう設計思想だから。本書で紹介される有名な「ジェリービーンズの実験」なんて、まさにそれです。
- 鼻をつまんでジェリービーンズを食べる → 甘い「味」しかしない
- 鼻から息を抜く → 口の中から喉を通って香りが鼻に抜け(口中嗅覚)、初めて「チェリー風味だ!」とわかる
私たちが「風味」だと思ってるものの正体は、実は口の中で感じる「匂い」。つまり、脳が味覚と嗅覚を合成して作り出した、壮大な「錯覚」だというわけです。私たちは毎日、脳に騙されて食事を楽しんでるってことですな。
で、ここからが本題。この無意識の感覚が、私たちの人生をどう左右しているのか。本書が突きつける事実は気持ち悪いぐらいに強烈です。
- 嫌悪と政治思想: 特に体臭に対して強い嫌悪感を持つ人ほど、保守的・権威主義的な政治思想に傾きやすい、という相関データがある。病原体を避けるための原始的な「嫌悪」という本能が、社会的な「異物」を排除しようとするイデオロギーに無意識下で結びついちゃう可能性がある
- 自己紹介としての匂い: 私たちが「いい匂い」と感じるものは、ほとんどが生まれ育った環境や文化で学習されたもの。つまり、あなたの好きな匂いのコレクションは、あなた自身の人生の物語を反映した「嗅覚の指紋」なんだ、と。嗅覚を失うことは、単に感覚が一つなくなるんじゃなく、自分のアイデンティティの一部が消し飛ぶに等しい
- 健康の早期警告システム: 嗅覚の低下は、アルツハイマー病やパーキンソン病といった神経変性疾患の、最も早期の兆候の一つであることが膨大な研究で示されている。認知機能の低下が明らかになる何年も前から、鼻はSOSを出し始めている。嗅覚系は、いわば「脳の健康状態を映し出す窓」。まさに「認知の炭鉱のカナリア」であり、全般的な死亡リスクの上昇とさえ関連がある
じゃあ、どうすりゃいいんだよ!って話としては、本書の最終章で希望を提示してくれておりました。結論から言うと、嗅覚は鍛えられる。オロフソン博士はそれを「鼻の体操(nasal gymnastics)」と呼んでいて、脳の神経可塑性を利用して、後天的にいくらでも鋭くできると断言しています。
博士の研究室では、嗅覚トレーニングを面白くするために、匂いを使った記憶ゲームや、VRのワインテイスティングゲーム、スマホアプリなんかを開発しているとのこと。驚くべきことに、こうした嗅覚トレーニングは、視覚的な記憶力まで改善するという転移効果まで確認されているらしい。もはやただの感覚トレーニングじゃなく、脳トレそのものっすね。
ということで、本書が教えてくれるのは、「もっと匂いに注意を払え」なんて単純な話じゃなくて、視覚情報に依存しきった現代社会で、私たちは最も原始的で、最も感情的で、最も正直な情報源をないがしろにしてきた。それこそが嗅覚、と。
プルーストが小説で「失われた時を求めて」マドレーヌの香りに過去を見出したように、私たちも意識的に鼻を使うことで、「失われた感覚」を取り戻せるのかもしれません。それは、食事をより深く味わい、人間関係を豊かにし、さらには自らの脳の健康を守ることにも繋がるってことですな。
本書で言うところの「鼻の賢者(nosewise)」になるってのは、世界の解像度を自ら上げていく、最高に知的な営みなんじゃないでしょうか。気になる方はぜひ。おすすめです。