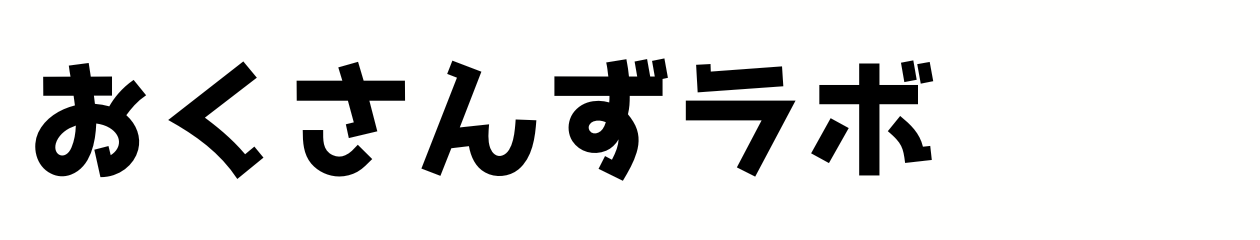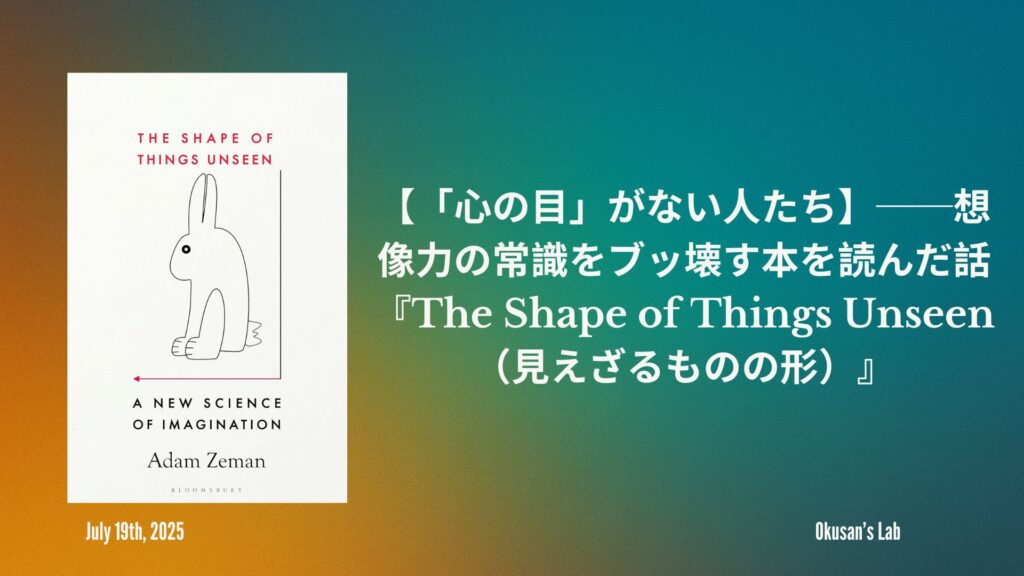
『The Shape of Things Unseen(見えざるものの形)』って本を読みました。著者は神経学者と哲学者の二足のわらじを履くアダム・ゼマン博士。私たちが「当たり前」だと思ってる「想像力」の概念を、根っこからひっくり返してくれる内容になっておりました。
「想像力」っていうと、アーティストとか作家とか、一部のクリエイティブな人たちの特殊能力みたいに思いがち。しかしゼマン博士は「いや、違うね」とバッサリ。「想像力こそが、人間の脳のデフォルト設定だ」って言うんですよ。
たしかに考えてみれば、私たちは一日の大半を「今、ここ」じゃないどこかで過ごしているはず。過去を思い出したり、週末の予定を立てたり、仕事の段取りを考えたり、妄想にふけったり。これは全部「想像力」の仕業。つまり、想像力は特別なもんじゃなくて、我々の意識のOSそのものなのだ、と。
ってな感じで、想像力に関していろいろ学びがあった本書から、脳みそが揺さぶられたポイントをまとめておきます。
🍎 頭の中にリンゴを「思い浮かべ」られますか?
いきなりですが、ちょっと試してみてください。目を閉じて、「赤いリンゴ」を思い浮かべられますか?
「まぁ、なんとなく見えるよ」って人が大半だと思います。しかし中には、「え?『思い浮かべる』って、ガチで絵が見えるの!?」って思った人もいるかもしれません。
この点、ゼマン博士が2015年に提唱したのが「アファンタジア(aphantasia)」という概念。これは、「心の目」が機能せず、意図的に頭の中に映像を思い描くことができない状態のこと。これは別に、病気や障害じゃなくて、人口の1〜4%にみられる人間の正常な変異なんだそうな。クラスに一人くらいはいる計算っすね。
(ちなみに、この研究のきっかけがまたドラマチックで、ある日、65歳の男性(MX患者)が、簡単な手術のあと、急に頭の中でイメージを見る能力を失ってゼマン博士のもとを訪れて、この症例を報告したら、「先生、私は生まれつき見えません!」って人からの連絡が殺到したらしい)
つまり、「頭の中に絵なんて浮かばないのが普通だと思ってた」って人が世の中には思っている以上にゴロゴロいて、彼らは「リンゴを思い浮かべて」って言われたら、リンゴの「概念」とか「情報」を頭の中で整理するだけなんだ、と。逆に、“見える”側の人たちも、「みんな見えてるに決まってる」って思い込んでいる。自分の「当たり前」が、決して万人のものじゃないってわけですね。この辺りは、グランディン先生の「ビジュアルシンカーの脳」とも重なるところがありますな。
🧠 「事実として記憶する人」と「過去にタイムスリップする人」
面白いのが、この想像力にはスペクトラムがあるってこと。アファンタジアの対極には、「ハイパーファンタジア」っていう、現実と見紛うほど鮮明なイメージを見られる人たちもいる。
この両極端の人たちを比べると、脳の使い方が全然違うことがわかってきてるそうで、これがまたおもろい。
- 自伝的記憶:
- アファンタジアの人:過去を「事実」として、情報ベースで記憶する。「何があったか」は知ってるけど、その場の空気や情景を感覚的に「再体験」はできない。
- ハイパーファンタジアの人:まるでタイムスリップしたかのように、過去の出来事を五感で豊かに「再体験」する
- 職業の傾向:
- アファンタジアの人:STEM分野に多い(思考が抽象的・概念的なんでしょうな)
- ハイパーファンタジアの人:クリエイティブな職業に惹かれる傾向がある
- 脳の活動(fMRI):
- アファンタジアの人:注意などを司る「前頭前皮質」と「視覚野」の連携が弱い。つまり、「見よう」という意志が、映像を生み出す部署にうまく伝わってない感じ。
- ハイパーファンタジアの人:この連携がめちゃくちゃ強い。
脳の配線が、記憶の仕方からキャリアの選択まで影響を与えてるってことで、人生にかなり大きな影響を与えそうな話ですねー。
🎨 「ビジョンを思い描け!」が通用しない世界
じゃあ、アファンタジアの人は創造的じゃないのか?というとこれがまた違うらしい。これは本書で説明されている最大のパラドックスでもあって、実は超有名な作家やクリエイターにもアファンタジアの人はいるんだそう。
彼らは「視覚化」に頼らずに、概念的な思考、言語的な推論、登場人物の感情の動きといった、別の戦略で創造性を発揮するらしい。ここで重要なのは、「想像力(Imagination)」と「視覚化(Visualization)」は別物だってことでしょう。アファンタジアは後者の欠如であって、前者まで失われたわけじゃない、と。
余談ですが、これは、教育やマネジメントの現場にいる人は、なかなか考えさせられる話じゃないでしょうか。「ビジョンを思い描いてみろ!」とか「情景が目に浮かぶように説明してくれ」みたいな指示を出す人がいますが、あれは“見える人”前提のコミュニケーションなんじゃないかと。人口の数パーセントには、まったく響いてないどころか、むしろ苦痛だったかもしれないわけですね。私たちが良かれと思って使ってる手法が、誰かにとっては「認知の壁」になってる可能性がある。これは、一種の“認知バイアス”であり、下手をすれば“認知的差別”とすら言えるかもしれないなーとか思いましたね。
ということでまとめると、この本が教えてくれるのは、「認知的謙虚さ」の重要性でしょう。我々が共有していると思っている「現実」や「常識」は、実は自分だけの脳が作り出した、きわめて個人的なものかもしれない、と。
私自身は、昔から「常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことだ」って言葉が好きだったんで、ある程度意識しているつもりではありましたが、この本を読んでからは一層、人と話すときに「この人の頭の中では、今どんな世界が広がってるんだろう?」って考えるようになりましたね。言葉の裏にある“見えない形”を想像する、みたいなイメージ。それこそが、相手を本当に理解しようとする「想像力」の正しい使い方なのかもしれないなー、と。
自分の物差しをいったん捨てることから、本当の対話は始まる。そんな、当たり前だけど忘れがちなことを、ガツンと叩き込まれた一冊でございました。かなりオススメです。