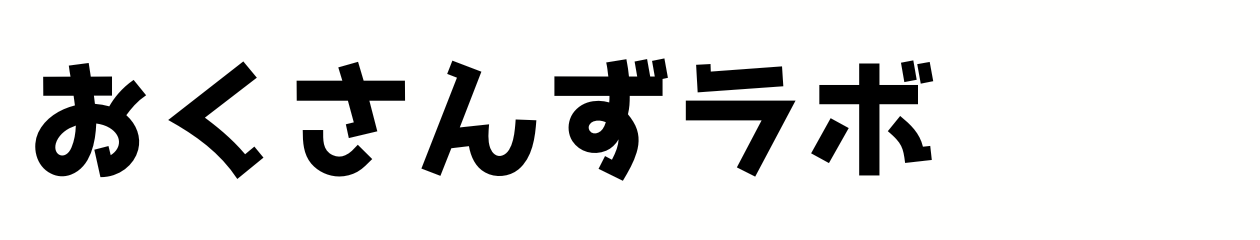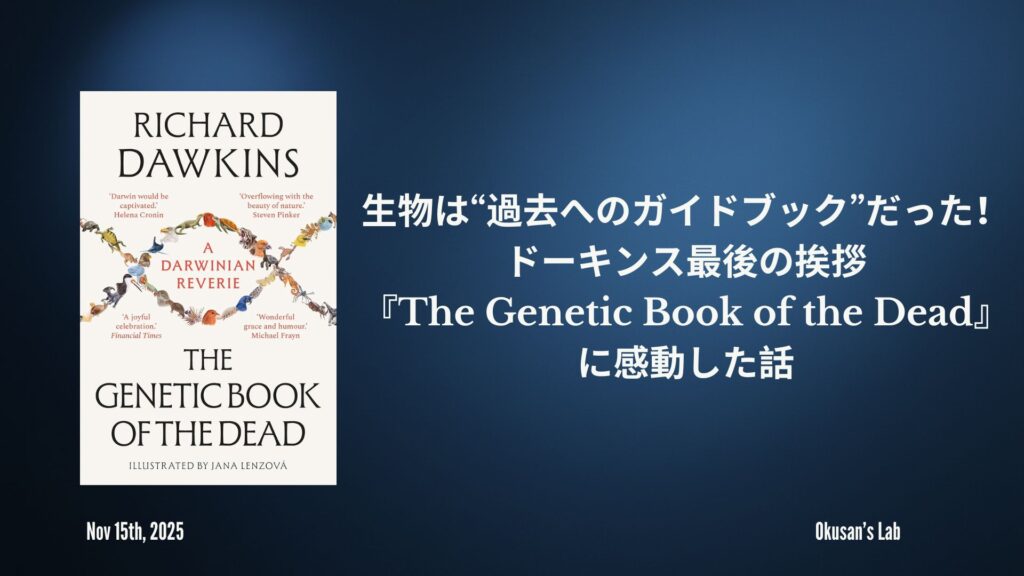
リチャード・ドーキンス先生の『The Genetic Book of the Dead』って本を読みました。知的な興奮が止まらない、久々にかなり感動した一冊でした。
ドーキンスといえば、もちろん『利己的な遺伝子』のあの人。現代最高の進化生物学者にして、最強の科学コミュニケーターの一人っすね。で、本書は彼が「The Final Bow(最後の挨拶)」と銘打った講演ツアーと並行して出た本でして、多くの批評家が「ドーキンスの白鳥の歌(swansong)」、つまり彼の知的キャリアの集大成だと位置づけてる一冊なんですな。
私にとって「ご冗談でしょう、ファインマンさん」って本が、科学の面白さ、物理法則の美しさを“発見”する純粋な喜びを教えてくれたバイブルなんですが、このドーキンスの本は、それとは別の種類の、壮大すぎる感動をもたらしてくれました。ファインマン先生が「今ここにある法則」の美しさを見せてくれたなら、ドーキンスは「今ここにある生命」に刻まれた「途方もない時間の歴史」を解読する興奮を見せつけてくれた感じですね(伝わるかな?)。
しかも、ヤナ・レンツォヴァーっていうイラストレーターによるカラー図版が満載で、本自体がもはや「芸術品(objet d'art)」。ドーキンスの「科学と文学(詩)こそが人類の最高到達点だ」っていう哲学を、ガチで体現しに来てるなーと。副題の「ダーウィン的夢想(A Darwinian Reverie)」ってのも伊達じゃない!って感じですね。
ということで、この興奮が冷めやらぬうちに、読みながらとっていたメモを整理しておきます。
- まず本書のど真ん中にあるメタファーが、美しすぎる。タイトル通り、すべての生物は古代エジプトの「死者の書」だ、と。ゲノムも、身体も、行動も、すべてが「その生物の祖先が生き抜いてきた“過去の世界”へのガイドブック」として読める、という
- さらにこのメタファーを、「パリンプセスト(Palimpsest)」という言葉で精緻化する。
- パリンプセストってのは、中世ヨーロッパで使われた羊皮紙のことで、古い文字を削り落として、その上に新しい文字を「重ね書き」した文書のこと。ポイントは、古い文字が完全には消えず、うっすら残ってる点
- これは進化の本質を突いていて、進化は「ゼロからの合理的設計」じゃなく、常に「すでにある祖先の構造」の上に“上書き”されていく。だから、古い歴史の痕跡が「不完全な設計」として絶対に残り続ける。これが、神による「インテリジェント・デザイン」を主張する人たちへの、ドーキンスからの最も強烈なカウンターパンチになっている
- この「生物=歴史的文書」ってのは、比喩じゃなくて、例えば、砂漠のトカゲの背中にある精巧なカモフラージュ模様。 あれは文字通り、祖先が何世代にもわたって捕食者から逃れてきた「古代の砂漠の風景」を、体表に「描いた絵画」そのもの。ラクダのゲノムは「砂漠で過ごした数千年」を記述してるし、モグラのDNAは「湿った地下の闇の世界」を雄弁に物語っている
- 「完璧な設計」だけが証拠じゃない。「不完全な設計」こそが、この「パリンプセスト」の最強の証拠だ、という点がまた熱い。ドーキンスの十八番、「キリンの反回喉頭神経」がここでも登場する
- 脳から喉(発声器)に行く神経が、なぜか最短距離を通らず、わざわざ首をずーっと下って、心臓の大動脈をUターンしてから、また首を上って喉に達する。アホみたいな非効率さ。 合理的な設計者なら絶対こんなことしない
- これこそ、我々の祖先が「魚類」だった時代の神経経路(エラ呼吸用)を、進化の過程でそのまま引きずり、首が長くなるにつれて非合理的に引き伸ばされた「歴史の傷跡」。この“不合理さ”こそが、我々が「上書き」された文書であることの動かぬ証拠だ、と。いやはや、痛快
- こういう「歴史の偶然性」を重視するグールドみたいな論者(「生命のテープを巻き戻したら、全く異なる結果になる」)に対して、ドーキンスは「そんなこたぁない」とバッサリ。その反論の柱が「収斂進化(Convergent Evolution)」
- 遺伝的にはめちゃくちゃ遠いのに、同じような環境(生態的ニッチ)に適応すると、驚くほどソックリな「解決策」にたどり着く例が多すぎだろ、と
- 代表例が、オーストラリアの有袋類(フクロモモンガ、フクロモグラ、絶滅したフクロオオカミ)と、他の大陸の有胎盤類(モモンガ、モグラ、オオカミ)。 隔離された大陸で独立に進化したのに、姿形がウリ二つ。他にも、飛翔能力(コウモリ、鳥、昆虫)や電気器官(デンキウナギなど)は、系統樹の全然違う場所で、何度も何度も独立に“発明”されてる
- これは、環境による淘汰圧が「単なる偶然」を凌駕して、生物を特定の「最適解」へと強く“引き寄せる”力が働いてるって証拠。物理法則が、厳密な「解」を生物に要求してる。この視点も強烈
- で、本書の白眉が、カッコウの托卵(自分の卵を他の鳥の巣に産む)の事例。ここには、遺伝子がどうやって「歴史」を記録するかの、精緻な暗号解読ミステリーがある
- 【問題】
- 1. カッコウのメスは、特定の宿主(コマドリとか)の卵に、色も模様もそっくりな卵を産む「専門家」に分化してる
- 2. メスは、自分が育てられた宿主の巣に産卵する傾向がある
- なのに、オスはメスがどの専門家かに関係なく、「無差別」に交尾する
- 「コマドリ専門」のメスが「アカクロウタドリ専門」の家系のオスと交尾したら、その娘の遺伝子は「希釈」されて、どっちつかずの中途半端な卵しか産めなくなるはず。宿主に見破られて淘汰されちゃう。なのになぜ、こんな高度な専門分化が維持できるのか?
- 【解答】この謎を解くカギが、なんと「性染色体」にあった
- 哺乳類はオスがXY、メスがXX。でも鳥類は逆で、オスがZZ、メスがZW。つまり、メスだけが「W染色体」を持ってる
- そして卵の擬態(色や模様)を制御する遺伝子は、このW染色体の上にあった!
- W染色体は、母から娘へと、母系でのみ受け継がれる。だから、オスの遺伝子による「希釈(汚染)」を完全に免れる!
- コマドリの巣に卵を産むメスは、そのW染色体を、過去何世代にもわたってコマドリの巣で托卵に成功してきた「母系の祖先」からのみ受け継いでる。これぞ「後方を見る遺伝子の視点」。遺伝子が、自らの成功した「母系の歴史」だけを文字通り“記録”し、“参照”して適応してる。壮大すぎて、鳥肌が立ちました…。
- 【問題】
- もちろん、ただ美しい自然科学の話で終わらないのがドーキンス。本書は、彼の理論(遺伝子中心主義)に対する批判者(特にデニス・ノーブル)への、徹底的な「防衛戦」の書でもある。「“遺伝子は生物に使われるだけだ”って? そんなの“真実だが、些末なことだ(true but trivial)”」とバッサリ斬り捨ててる(この戦闘的な姿勢は相変わらずで安心します笑)
- そして最後の最後、最終章で提示される概念が、最もラディカルで、ドーキンスの思索の壮大な結論になっている
- 彼が提示する新造語が「Verticoviruses(垂直伝播ウイルス)」ドーキンスに言わせれば、我々のゲノムを構成するすべての「良き遺伝子」は、本質的に「垂直伝播ウイルス」の巨大なコロニーなんだ、と。
- どういうことか? 我々が知る“悪い”ウイルス(コロナやインフル)は、「Horizonto viruses(水平伝播ウイルス)」。個体から個体へと水平に飛び移れる。だから宿主の個体は「使い捨て」で、宿主を殺してでも次に移る戦略(=強毒性)が合理的になりうる
- でも、私たちの「良き遺伝子」は、親から子へ(垂直に)しか伝播できない。水平伝播という「逃げ道」がない。
- だから、彼らが未来へ到達する唯一の方法は、その乗り物(=俺ら生物個体)が生存し、首尾よく繁殖すること。
- その結果、垂直伝播する遺伝子たちは、互いに「協調」し、乗り物の生存と繁殖を最大化するように進化せざるを得なかった
- これこそが、『利己的な遺伝子』の究極のパラドックスへの答えなのだ、と。「遺伝子は利己的(自己複製が目的)」だけど、その伝播様式が「垂直」に限定されてるがゆえに、その利己的な目的を達成する最良の戦略が「(他の遺伝子や宿主との)協調」になる
- 我々のゲノムとは、そういう「協調戦略」を採用した、古代ウイルスの巨大なコロニーに他ならない…。スケールがデカすぎて言葉を失います。。
ということで、本書はドーキンスの半世紀にわたるキャリアの、論理的帰結であり、壮大な集大成でございました。ファインマン先生が物理法則の美しさを「発見」する喜びを体現した天才なら、ドーキンスは生命の歴史という「記録」を「解読」する執念を体現した天才、と言えるんじゃないでしょうか。
AIが“未来”を予測しようと躍起になってるこの時代に、ドーキンスは「今、ここにある生命」を極限まで深く読み解くことで、“過去のすべて”を見通そうとしている。この視点の逆転が強烈に面白い。
この本を読んだ後だと、マジで世界の見え方が変わりますね。
公園で見るハトも、道端の雑草も、なんなら自分自身のこの体も、すべてが「数十億年の歴史を刻み込んだ、生きたパリンプセスト(重ね書き文書)」に見えてくる。
キリンの神経の話なんて、ウチの大学や多くの大企業が抱えてる「歴史的経緯で誰も触れないレガシーシステム」と全く同じ構造じゃないすか?とか、妙に生々しい皮肉まで浮かんできます。
自分が時々感じる“不合理な”感情や衝動も、もしかしたらそれは、祖先が生き抜いた“過去の環境”の記録(ネガフィルム)なのかもしれない…。そう考えると、単なる自己啓発とは違う次元で、自己理解が深まる気がします。
これが本当に彼の「最後の挨拶」なら、それはダーウィン的自然観への、最も美しく、最も戦闘的な賛歌でしょう。いやはや科学的ロマンの最高峰。
積読しているうちに邦訳版も出ていたようです(見たところ原書の方が安そうなので、英語に抵抗ない方は原書で読んでみるのもありかも)。全人類にぜひ読んでほしい一冊。激しくおすすめ。