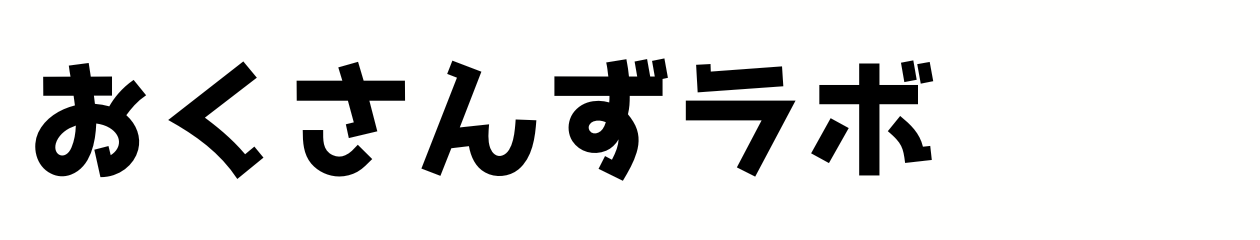ノーベル賞受賞者が自らの発見を語る、みたいな本ってあるじゃないですか。正直、当たり外れがデカいジャンルだなーと個人的に思ってまして、下手するとただの自慢話か、難解すぎて読者を置き去りにするかのどっちかになりがちなんすよね。で、今回読んだのがトーマス・チェック博士の『The Catalyst』って本(バーガー先生の説得の本とは無関係)。この人も1989年にノーベル化学賞を獲ったガチの大物ですが、結論から言うと、この本は「大当たり」でございました。
博士はRNA研究の革命を起こした人物であると同時に、本書の主人公でもあるわけで、いわば歴史上の人物が自らペンを取って歴史を語るようなもの。しかも、大学1年生に化学を教えてきた経験からか、文章がめちゃくちゃ分かりやすい。生命の根源的な謎から最新医療までを「RNA」っていう一本の線でつないで、壮大な物語に仕立て上げられておりました。
ということで、いつもどおり本書の要点やら感想やらをつらつらまとめておきます。
まず大前提として、(今でもある程度そうだと思いますが)私たちが学校で習った生物学ってのは、完全にDNAが主役の世界でしたよね。DNAは生命のすべてが書き込まれた「設計図」で、絶対的な支配者。で、タンパク質がその設計図どおりに働く「労働者」。じゃあRNAは何かっていうと、設計図の情報を工場に運ぶだけの「メッセンジャー(使いっ走り)」。このDNA独裁政権とも言える「セントラルドグマ(DNA→RNA→タンパク質)」が、20世紀の生物学の常識だったわけです。本書が描くのは、この下っ端だと思われていたRNAが、とんでもない能力を隠し持っていて、ついには王座をひっくり返しちまう、っていう壮大な下克上の物語。
その革命の引き金となったのが、チェック博士自身の発見です。博士は、テトラヒメナっていう池の中にいる単細胞生物(ゾウリムシの仲間みたいなもん)を研究してたんですが、ある奇妙な現象にぶち当たります。この生物のRNAを、タンパク質が一切存在しない「空っぽの試験管」に入れたところ、なんとRNAが自分自身で、自分の一部を切り貼りし始めたですな。これは科学界にとって衝撃的な事件でした。なぜなら、化学反応を進める「酵素」は、すべてタンパク質でできている、ってのが鉄則だったから。なのに、使いっ走りのはずのRNAが、自らハサミとノリを持って編集作業を始めた。これはつまり、RNAが「触媒(カタリスト)」、すなわち酵素としても機能することを意味します。博士が「リボザイム」と名付けたこの発見によって、「すべての酵素はタンパク質である」という生物学の常識が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちた瞬間っすね。
この「RNAは酵素にもなれる」って発見は、単に生物学の教科書を一行書き換えた、って話じゃあ終わりません。生命の起源にまつわる、「鶏が先か、卵が先か」問題に、強烈な答えを突きつけたわけです。生命の誕生には、設計図のDNAと、働くためのタンパク質が必要だけど、DNAを複製するにはタンパク質酵素が必要だし、タンパク質を作るにはDNAの指示が必要……じゃあ、どっちが先にできたんだよ!ってパラドックスですね。ここに登場するのがRNA。RNAは、DNAのように遺伝情報を保存できるし、タンパク質のように化学反応も触媒できる。つまり、一人二役をこなせる。この発見から、「太古の地球では、まずRNAが生命活動のすべてを担っていたのではないか?」という「RNAワールド仮説」が生まれました。生命の最初の役者は、DNAでもタンパク質でもなく、RNAだった。この仮説は、今や生命起源論の最も有力なシナリオの一つになってるのはご存じの方も多いでしょう。
で、こういう基礎科学の話って「だから何なの?俺の生活に何の関係が?」って思われがち。本書の真骨頂はここから。この「RNA、実は何でもできる説」が、現代医療の最前線を根底から支えている、という現実を叩きつけてきます。有名どこだけでも、
- mRNAワクチン: COVID-19で一躍有名になったが、あれこそRNA研究の集大成。ウイルスの設計図の一部をmRNAとして体内に送り込み、我々の細胞に「敵の顔」を覚えさせる。何十年も続いた池の微生物の研究が、パンデミックから人類を救う切り札になった
- CRISPR: 「遺伝子編集」技術。これも実はRNAが主役。ガイドRNAと呼ばれる分子が、まるでGPSのようにゲノムの特定の位置に「切れ!」と命令するハサミ(Cas酵素)を連れてくる仕組み。遺伝病の治療に革命を起こすと期待されている。
- RNAi(RNA干渉): 特定の遺伝子の働きを「オフ」にする技術。病気の原因になる悪玉タンパク質の生産を、その設計図を読む段階でストップさせられる。いわば、遺伝子のボリュームをピンポイントでゼロにするスイッチみたいなもの
重要なのは、これらの画期的な治療法が、「病気を治そう!」という目的で始まった研究から生まれたわけじゃないってことでしょう。チェック博士の発見も、最初はただの知的好奇心。線虫の遺伝子を調べてたらRNAiが見つかり、細菌の免疫を調べてたらCRISPRが見つかった。役に立つかどうかなんて分からない基礎研究の積み重ねが、何十年も経ってから、とんでもない形で花開いている。短期的な成果ばかり求める風潮への、強烈な皮肉にも聞こえますね。
ということで、本書は単なる科学解説書に収まらず、RNAという分子を主人公にした、壮大な発見の物語であり、科学がどうやって進歩し、我々の生活を変えていくのかを生々しく描いたドキュメンタリーのような印象を受けました。
個人的に思ったのは、私たちはあまりに長い間、「設計図(DNA)」ばかりを神聖視しすぎていたんじゃないか、ってこと。でも現実は、その設計図を読み、解釈し、時には勝手に編集し、実行に移す「現場監督(RNA)」の方がよっぽどダイナミックで、生命の本質を握っていた。これは生物学以外の文脈のアナロジーとしてもかなり使えそうだなーってのを感じましたね。計画書や戦略マップを眺めて悦に入るより、現場でそれをどう動かすかっていう「実行知」にこそ、物事を動かす本当の力があるのかもしれない、と。私たちは案外、生命の秘密に限らず、いろんなことで「見るべき場所」を間違えてるのかもしれません。そんな考えを巡らせるような読書(思考)体験でございました。