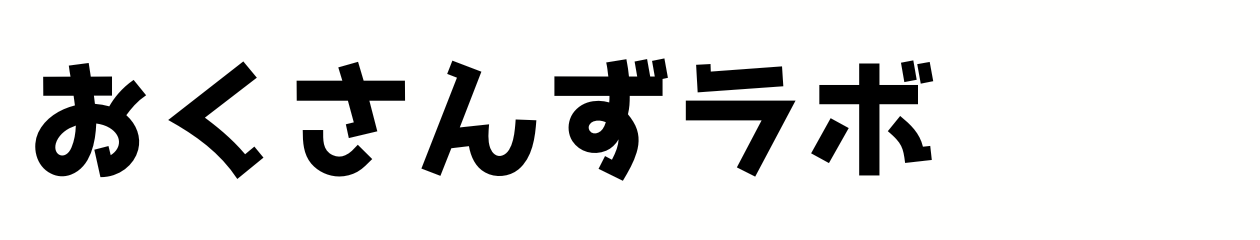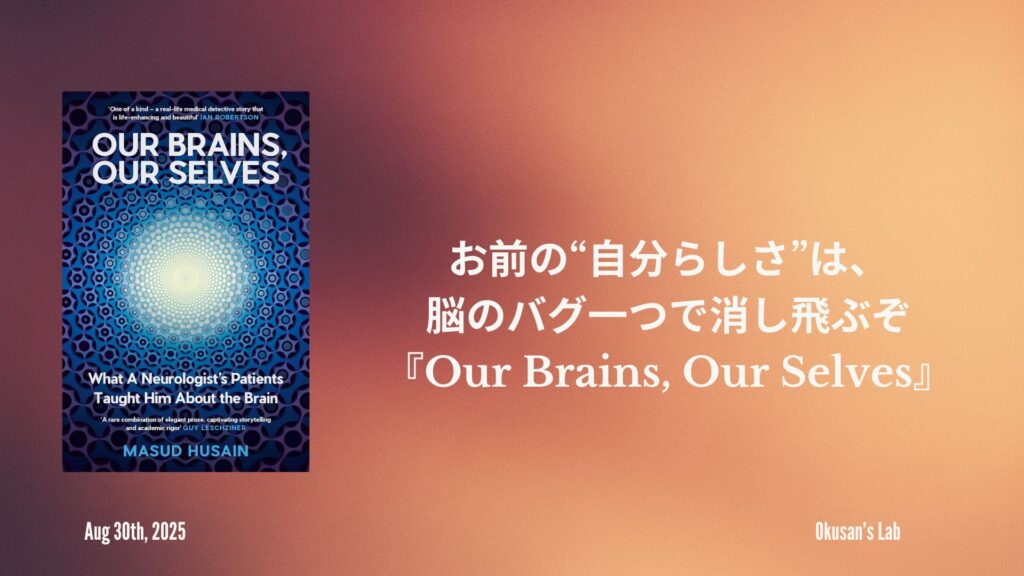
今週もまた脳科学の本を読んでおりました。今回は、マスード・フセイン先生っていう、オックスフォード大学の神経学教授が書いた『Our Brains, Our Selves』(我々の脳、我々の自己)って本。正直2025年で読んだ本の中でもトップクラスに足元を揺さぶられるような一冊でございました。
著者のフセイン教授は、神経学の分野で世界最高峰のジャーナル『Brain』の編集長も務める、まさにこの世界の“ラスボス”みたいな人物。しかも、最新の研究をゴリゴリ進める科学者の顔と、実際に脳卒中や認知症の患者と向き合う臨床医の顔を両方持っておられる。この「現場感」と「最先端の知見」がハイブリッドになってることもあって、本書の説得力がえげつないことになっておりました。
で、この本が何を言ってるかっていうと、身も蓋もない一言に集約されるんじゃないかと。それはつまり、
「お前が“自分”だと思っているものは、脳が生み出す不安定な現象にすぎない」
ってこと。我々の人格、意欲、記憶、愛情さえも、脳の特定の回路が正常に動いているおかげで成り立っている「借り物」でしかないんだ、と。その証拠として、脳にほんの少しのダメージを負っただけで、“自分らしさ”が根こそぎ変わってしまった患者たちの物語が、これでもかと突きつけられるわけです。
ってことで、以下ではいくつか、本書から脳みそを揺さぶられたポイントをまとめておきましょうー。
- まず衝撃的なのが、「やる気は根性論ではなく、脳の物理的なスイッチの問題だ」ってことを示すケース。
もともとエリートで社交的だった若い男性が、ある日、脳の奥深くにある「腹側淡蒼球」っていう(やる気スイッチみたいな)場所に、ごく小さな脳卒中を起こす。するとどうなるか。彼は、文字通り“モチベーション”という感情をすべて失ってしまうんですよ。仕事はもちろん、失業手当を申請する気力さえ湧かず、ただ部屋でボーッとするだけ。友人たちは「怠けてるだけだ」と彼を責め、次々と去っていく。
これは、自己啓発書とかに書いてある「マインドセットを変えろ!」みたいな話が、いかに無力かを物語っているなーと。彼の“やる気”は、脳の配線が物理的に切断されたことで消えただけ。そして話のキモは、この症状が「脳の報酬系を刺激する薬」を投与したことで、劇的に回復するってところ。つまり、意志の力なんて精神論はクソ食らえで、人間の意欲は脳内の化学物質と回路で完全に説明がつくって現実を、これ以上なくクリアに見せつけられるわけです。 - 次に印象的だったのが、「“良識ある人格”とは、脳が必死に“暴走”を抑え込んだ結果にすぎない」という話。もともと内気でシャイだった女性が、前頭側頭型認知症っていう、人格や社会性を司る前頭葉が溶けていく病気にかかってしまう。すると彼女は、派手な服を着て街中で見知らぬ人を罵倒するような、抑制の効かない人物に180度変わってしまった。
これは、私たちが「あの人らしいね」って言ってる“人格”の正体が、実は前頭葉っていう“猛獣使い”が、衝動的な本能っていう“猛獣”に必死で首輪をつけている状態だってことの証明。その首輪が壊れた瞬間、社会性とか共感とか、そういう“後付けのOS”は全部吹き飛んで、もっと原始的な自分が顔を出す。我々が社会生活を送れているのは、ただ前頭葉が正常に機能してくれているから。それだけのことなんだなーと実感しましたね。 - さらに、「愛や記憶すら、脳が即興で作る“物語”でしかない」という現実も強烈。アルツハイマー病の女性が、長年連れ添った夫の顔を見ても、それが夫だと認識できなくなる。いや、顔はわかるんですよ。でも、それに伴うはずの「親近感」とか「愛情」といった感情が湧いてこない。脳が「知ってる顔」と「知らない感じ」の矛盾を解決できなくなった結果、彼女はどういう結論に至ったか。「こいつは夫のフリをした偽物だ」と妄想の物語を作り上げて、夫を拒絶し始める。
私たちのアイデンティティってのは、過去の記憶をつなぎ合わせて作られた一本の映画みたいなもの。そのフィルムが破損したり、特定のシーン(感情)が再生されなくなったりすると、脳は辻褄を合わせるために、平気でストーリーを書き換えてしまう。我々が信じている「揺るぎない夫婦の絆」みたいなものですら、脳の物語生成機能に依存した、極めて脆いものだというわけです。
本書には、他にも「自分の手が自分のものではないと感じる女性」の話が出てきます。これは、心と体が一体であるというデカルト以来の哲学的な常識を、脳のバグ一つが木っ端微塵にする事例っすね。「私」が「私の体」を所有しているという感覚すら、脳が作り出す当たり前じゃない“達成”の一つに過ぎなかった。
こうして見ると、フセイン教授がやってるのは、もはや臨床というメスを使った哲学のように見えてきます。デカルトとかヒュームとかが机の上でこねくり回してきた「自己とは何か?」っていう問いに、「うるせえ、これが現場の答えだ」とばかりに、患者たちの生々しい現実を叩きつけていく。
本書が暗に示しているのは、「自己」なんて単一の固いものがあるわけじゃないってこと。というよりもむしろ、
- 身体的所有感(これは私の体だ)
- 動機付け(私はこれがしたい)
- 社会的抑制(これを言ったらマズい)
- 物語的記憶(私はこういう人生を歩んできた)
といった機能の“連合体”みたいなもんなんでしょう。この一つでも欠けると、「自分」という感覚は簡単に崩壊してしまう。私たちが立っている地面は、想像以上にグラグラだったわけですね。
じゃあ、この本を読んで絶望すればいいのかっていうと、そうでもなくて、希望のヒントも見えてきます。
この本が突きつけるのは、人間の脆さであると同時に、新しい“優しさ”の可能性でもあると感じましたね。私たちは、やる気のない人を見ると「怠け者」と断罪し、突飛な行動をする人を見ると「社会の迷惑者」と眉をひそめ、物忘れの激しい老人を「ボケている」と突き放す。これってのは、全部道徳的なジャッジでしょう。
しかし、フセイン教授の視点を拝借するとその見方が変わる。「あの人のやる気がないのは、腹側淡蒼球の機能が落ちてるのかもしれない」「あの人が怒りっぽいのは、前頭葉の抑制が効かなくなっているだけかもしれない」という診断的な視点に切り替わってきます。
相手の行動を免罪するって話じゃなくて、ただ、私たちの非難や説教がいかに無意味で、的外れであるかを教えてくれるんですな。そして、私たちがすべきことは道徳的なジャッジを下すことではなく、その人の脳内で何が起きているかを理解し、医学的・社会的なサポートを考えることなんだ、と。
ってことでまとめると、本書は単に脳科学の最先端を教えてくれるだけじゃなくて、人間の“バグ”を理解することが、いかに私たちを賢く、優しくしてくれるかを示す、最高の処方箋なんじゃないかと。邦訳版もそのうち出ると思います。気になる方はぜひ。世界の見え方がきっと変わるはずでございます。