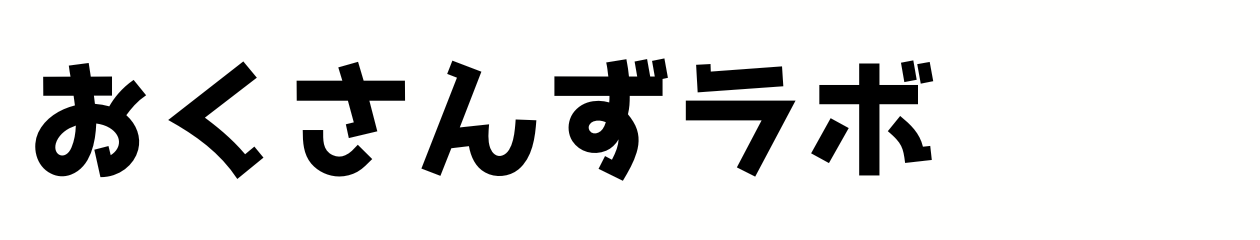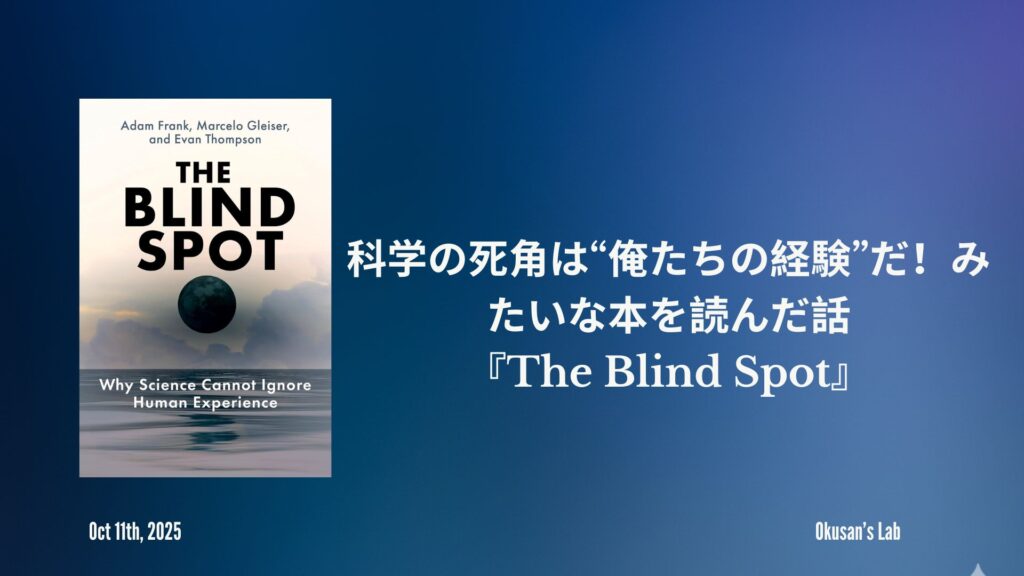
『The Blind Spot: Why Science Cannot Ignore Human Experience』って本を読みました。サイケデリック神経科学の第一人者であるロビン・カーハート=ハリス教授が「I agree」とツイートしてるのを見て、「これは読まないわけにはいかないっしょ!」と飛びついた一冊。著者は宇宙物理学者2人(アダム・フランク、マルセロ・グライサー)と現象学の哲学者(エヴァン・トンプソン)で、異種格闘技戦みたいなチームっすね。
で、この本が何を言ってるかと言いますと、一言で言えば「現代科学は、自分たちの土台であるはずの“人間の経験”を都合よく無視してきたせいで袋小路に迷い込んでるぞ!」という、科学の根幹への強烈なダメ出しです。気候変動から意識の謎まで、現代社会が抱えるデカい問題は、元をたどれば全部この科学の「盲点」に行き着く、みたいなラディカルな主張を展開しておりまして、かなり刺激的でした。
ということで、本書から参考になったポイントをまとめておきます。
- まず著者たちが指摘するのは、現代科学がもたらした「意味の危機」。科学は、一方では、「138億年の宇宙の歴史から見れば、人間なんて辺境の惑星に生まれたただの塵芥だ」と我々を矮小化する。ところが他方で、量子力学なんかは「観察者(つまり人間)がどう測定するかで現実が決まる」みたいなことを言い出す。つまり科学は、「お前は宇宙のゴミだ!」と言いながら、「でも世界の中心にはお前がいる!」とも言ってるわけで、この壮大な自己矛盾が、現代人の「俺たち、何のために生きてんの?」っていう虚しさに繋がってるんじゃないか、と。
- じゃあ、なんでこんな矛盾が生まれたのか? その根本原因こそが、本書のタイトルにもなってる「盲点(The Blind Spot)」。人間の眼には物理的に何も見えない「盲点」があるけど、まさにその構造があるからこそ「見ること」が可能になる。それと同じで、科学にも、科学的探求そのものを可能にしているのに、科学自身から完全に見過ごされてきた盲点がある。それが「直接的な経験(direct experience)」だと。色、音、感情、思考といった、私たちが今まさに生きて感じているこの経験こそが、あらゆる科学的測定や理論化の絶対的な出発点のはずなのに、科学は「客観性」という錦の御旗のもと、それを探求の対象から追放してしまった
- これは、科学者が陥りがちな「神の視点」という幻想への痛烈な批判でもある。まるで自分が世界の“外”から全てを客観的に眺められるかのような態度。しかし著者たちは、「そんな視点はありえない」とバッサリ斬る。我々は宇宙の外には出られないし、素粒子の振る舞いも我々の問い方と切り離せない。つまり、科学っていうのは絶対的な真理のコピーなんかじゃなく、「世界と我々の経験が共に進化しながら作り上げる、自己修正的な物語」に過ぎないんだ、と。(この方がよっぽど誠実で、カッコいい科学観じゃないかと思いましたね)
- この「経験の排除」は、哲学的な問題にとどまらない。著者たちによれば、現代の環境危機も、この科学の“盲点”が生み出した論理的帰結だという。どういうことかと言うと、
- 科学が「経験」を追放したことで、自然から色や音、匂いといった質的な価値が剥ぎ取られた
- 価値を失った自然は、測定・操作・利用されるためだけの単なる「客体(オブジェクト)」、つまり「資源」に成り下がった
- 「自然=資源」という世界観が、産業革命以降の無限の環境搾取を正当化し、加速させた
- その結果が、今の気候変動や生物多様性の喪失だ、と。つまり、環境問題は単なる技術や政策の失敗じゃなく、我々の文明の根底にある科学的世界観そのものに由来する“病”だと。
- じゃあ、具体的に科学をダメにした「哲学的誤謬」は何か? 本書ではいくつか挙げられているが、特に重要なのが「自然の二元論」と「数学的実体の具体化」の2つ。
- 自然の二元論:ガリレオとかデカルトが、「世界は数学で書ける客観的な“一次性質”と、心の中にしかない主観的な“二次性質”(色とか香り)に分けられる」って言っちゃったのが全ての始まり。これによって、豊かで具体的な経験の世界が、科学が扱うべき“リアル”な世界から追放された
- 数学的実体の具体化:これは「地図と現地を混同するな」って話。例えば、アインシュタインの相対性理論から導かれる「ブロック宇宙」っていう数学モデルは、時間が静的な塊であるかのように描く。これを真に受けた物理学者が「時間の流れは幻想だ!」とか言い出すわけだが、著者たちは「ふざけるな、我々が経験するダイナミックな“時間の流れ”こそが現実(現地)で、お前の理論(地図)はそれを記述するための一つの側面に過ぎないだろ!」とツッコミを入れる
- この視点に立つと、これまでバラバラに見えていた科学の難問が、全部同じ根っこで繋がって見えてくる
- 量子測定問題(なぜ観測すると現実が決まるのか?):知る者(経験)と知られるもの(量子)を最初から分離するからワケがわからなくなる
- 意識のハードプロブレム(なぜ脳の物理現象から主観的経験が生まれるのか?):これも物質(客観)と経験(主観)を分離した「自然の二元論」が生んだ人工的な問題
- 生命とは何か:生命をDNAっていう設計図で動く分子機械と見る還元主義じゃ、自らを内側から作り維持する「生物学的自律性」という、まさに“生きている”経験の本質を捉えきれない。全部、「盲点」である“経験”を無視したツケが回ってきてるだけ
- じゃあどうすればいいのか? 著者たちは、科学理論を捨てろなんて言ってない。彼らが問題視しているのは、科学の成果に対する「哲学的過剰解釈」、つまり物理主義や還元主義に凝り固まった硬直した世界観の方。彼らが目指すのは、科学と人文知の再融合。人間を、自然から切り離された観察者としてではなく、「自然が自らを理解するための器官」として捉え直す(この詩的な表現にはシビれましたね。私たち人間は、自然の中から生まれ、自然の一部として、自然自身が「俺って何だろう?」と考えるための“アンテナ”みたいなもんなのかもしれません)
ということで、本書は別に単なる科学批判の本じゃあなくて、「客観性」って言葉を疑い、自分自身の「経験」という揺るぎない土台に立ち返ることを促す、哲学的な一冊でした。科学が紡ぎ出す「物語」を、私たちはこれからどう書き換えていくべきなのか。そんな壮大な問いを突きつけられたような感覚ですね。
ぶっちゃけ、議論の構成がちょっと複雑で、専門用語も多いので万人におすすめできるかは微妙なラインです。が、科学の現状にどこか違和感を持っていたり、意識の問題や環境問題の根源に関心があったりする人にとっては、間違いなく世界の見え方を変える一撃になるはず。個人的には、今年読んだ中でもトップクラスに刺激的な本でございました。