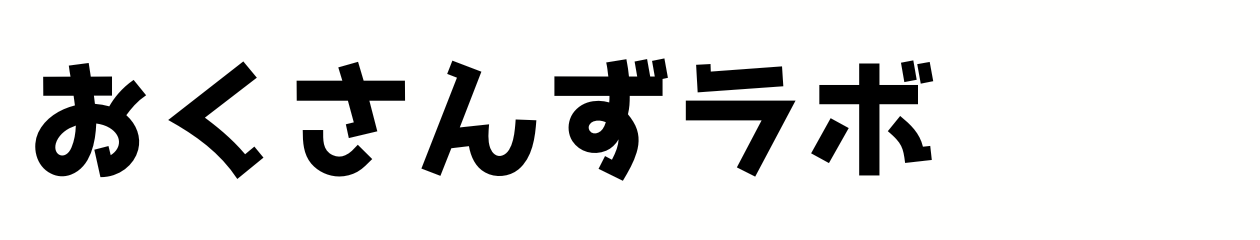ダニエル・ヨン博士の『A Trick of the Mind』って本を読みました。著者はロンドン大学の認知神経科学者でして、「不確実性ラボ」って名前の研究室を率いるガチの研究者っすね。で、本書はその道のプロが「我々の脳は現実をありのままに見てるんじゃなく、積極的に“発明”してるんだぜ」といった趣旨の内容になっておりました。
なんでも、我々の知覚は「制御された幻覚」であって、客観的な現実なんてものは幻想に過ぎない、と。この手の話は下手をするとスピリチュアルに流れがちですけど、本書は最新の神経科学でそのメカニズムをバッサリと解き明かしてくれてるんで最後まで楽しく読めました。
ということで、以下ではいつもどおり本書から参考になったポイントをまとめておきます。
まず大前提として、本書が提示する脳のモデルが秀逸。それは「頭蓋骨の中に閉じ込められた科学者」という比喩。どういうことかと言うと、
あなたの脳は、頭蓋骨という暗闇の部屋に閉じ込められていて、外の世界を直接見ることはできません。脳に届くのは、目や耳から送られてくる、不完全でノイズだらけの電気信号だけ。じゃあ、どうやって世界を理解するのか?
脳は、過去の経験から「世界ってのは、たぶんこうなってるだろう」という仮説(予測)をまず立てるんです。そして、感覚器官から入ってくるデータが、その仮説とどれくらい「ズレているか」だけをチェックする。この「ズレ」のことを「予測誤差」と呼びます。
つまり、脳が処理しているのは、現実そのものじゃなくて、「予測と現実の差分」だけ。これは、まさに科学者がやること。仮説を立てて、実験結果との誤差を検証して、仮説をアップデートしていく。あなたの脳は、毎日24時間、この地道な科学的検証を無意識にやり続けている、健気な科学者なんだ、というわけです。
この「予測する脳」モデルを通して考えてみると、日常のいろんなことが見えてきます。例えば、「なぜあなたの目はあなたにウソをつくのか?」という話。
視野には、神経が束になっているせいで物理的に何も見えない「盲点」がありますよね。でも、我々は普段、視野に「穴」が空いているなんてことは感じません。なぜか? 脳が「ここにはたぶん、周りと同じような模様が続いてるだろう」と勝手に予測して、その映像を補ってくれているからです。つまり、我々はそこにあるものを見ているんじゃなく、脳が見るはずだと「期待」したものを見ているに過ぎない。文字通り、脳は平気でウソをつき、我々はそれを現実だと思い込んでいるんですな。
夜空に奇妙な光を見たとき、UFOだと思うか、ドローンだと思うかもこれと同じ。脳は、過去のデータ(UFOは稀だけど、ドローンはよく飛んでる)と照らし合わせて、最も確率の高い説明(=予測誤差が最も少なくなる説明)を瞬時に採用する。合理的なようでいて、その判断基準はあなたの経験という偏ったデータベースに依存してるってのがミソですね。
で、面白いのがこの予測のメカニズムは、精神のあり方にまで影響を及ぼす、ってのがまた面白いところ。
例えば書籍の中では、「幻聴」を経験しやすい人々(霊能者や一部の精神疾患を持つ人)を調べたイェール大学の研究が紹介されています。彼らは、脳が作り出した「予測(事前期待)」の方を、現実の感覚データよりも強く信じてしまう傾向があったんだそうな。
これは、精神疾患を「脳が壊れている」という単純な話から解放するような視点だなーとか感じましたね。幻覚とは、何もないところに何かが付け加えられたのではなく、脳の「こうあるべきだ」という予測が暴走して、現実(何もない)を上書きしてしまった状態なんだ、と。つまり、あなたの「正気」も、脳が予測と現実のバランスをうまく取ってるだけの、綱渡りみたいなもの、というわけですね。違いは、脳内科学者の「仮説を信じる頑固さ」のチューニングがちょっと違うだけ、といった感じっすね。
さらに、この理屈は「なぜ人は陰謀論にハマるのか?」という現代的な問いにも、強烈な答えを提示してくれておりました。
パンデミックや政治不安みたいに、社会が不確実になると、我々の脳は「予測誤差」だらけになります。「何が起きるかわからない」という状態は、脳にとって非常に不快なわけです。
そこに、陰謀論が登場する。陰謀論は「すべての出来事は、実は〇〇という組織が裏で操っているのだ」という、シンプルで、万能で、強力な予測モデルを提供してくれます。
脳は、そのモデルが「真実か」どうかよりも、「予測誤差を減らして、世界を再び予測可能なものにしてくれるか」を優先する。だから、不確実性というストレスから逃れるために、その魅力的なモデルに飛びついてしまう。
これはめちゃくちゃ大事な視点なはずで、つまり、陰謀論者にファクトをぶつけてもムダなことが多いのは、彼らがアタマが悪いからじゃなく、彼らの脳が「予測できる安心感」という報酬にガッチリとロックされているからなんだ、と。論理と戦っているつもりが、相手は脳の生存本能と戦っている。そりゃあ、話が噛み合うわけないでしょうね。
余談ですけど、最近「チ。」でおなじみ魚豊先生の「ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ」っていう陰謀論にはまっていく青年のマンガを読んでいて、本書の内容と重ねて読むと面白いです。
話しを戻すと、じゃあ、このどうしようもない「脳のクセ」を知って、我々はどうすればいいのか? 本書が最後に示すのは、一種の「知的謙虚さ」と「共感」への道。
結局のところ、我々は一人ひとり、自分の人生経験という独自のデータセットで学習させた「自分だけの予測モデル」を使って、「自分だけが住む現実」を生きているわけです。
だとすれば、あなたと意見が合わない同僚や家族は、別に意地悪で言ってるわけでも、非合理的なわけでもないのかもしれない。ただ、あなたの脳にインストールされているOSと、相手の脳のOSが違うだけなのかもしれません。使っているデータベースが違えば、同じ情報を見ても、導き出される結論(予測)が違って当然でしょう。
この事実を理解できれば、意見の対立に出会ったとき、反射的に「こいつは間違ってる!」と断罪するのではなく、「相手の脳(世界モデル)は、どうしてそういう結論に至ったんだろう?」と、好奇心を持ってアプローチできるようになるはず。これこそが、この本が提供してくれる最強の処方箋なんじゃないかなーとか思いましたね。
ということで、本書はあなたの「頭蓋骨の中の科学者」をアップグレードするための、実践的なマニュアルとも取れるかもしれません。邦訳もそのうち出るでしょうから、気になる方はぜひどうぞ。おすすめです。