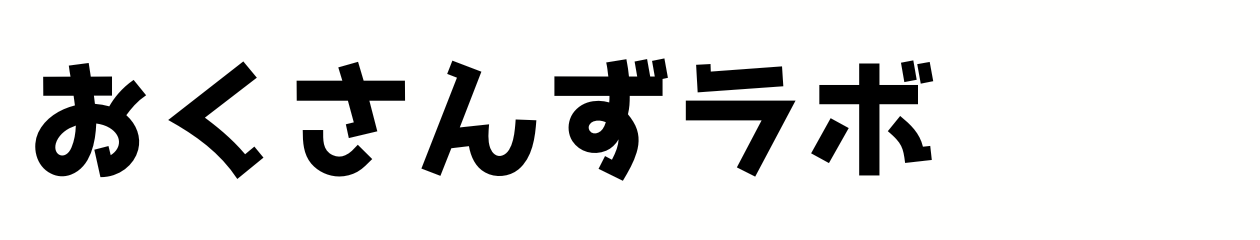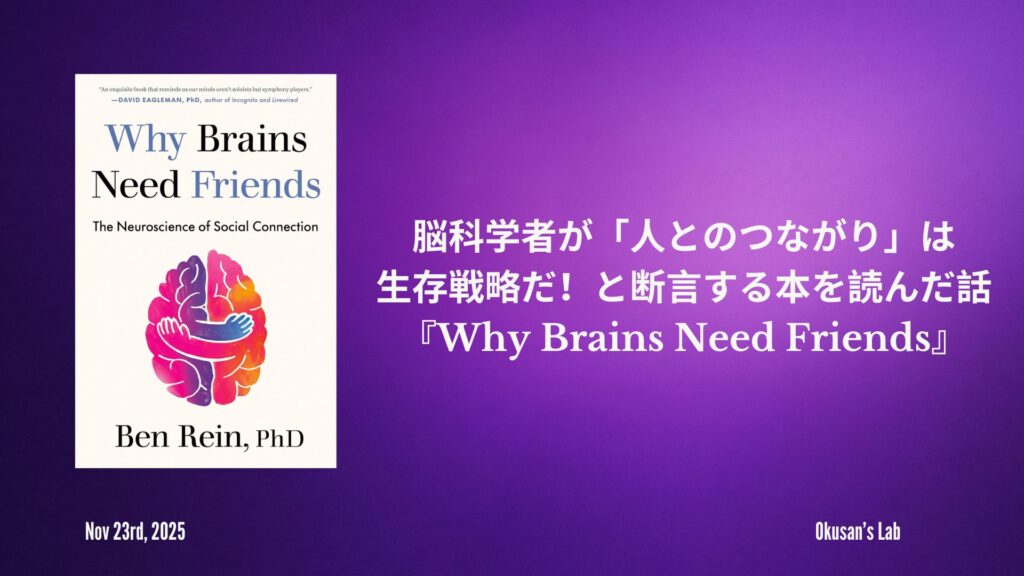
『Why Brains Need Friends(なぜ脳は友達を必要としているのか?)』って本を読みました。
著者はベン・レイン博士という、スタンフォード大やニューヨーク州立大バッファロー校で研究している神経科学者です。本書を読むまでは存じ上げなかったんですが、TikTokとかでも科学情報を発信してるらしく、説明がめちゃくちゃ上手いんですよ。
で、この本が何を言ってるかと言いますと、「友達作りは『趣味』じゃなくて『生存戦略』だぞ!」って話です。私たちは通常、社会的つながりを「あったらいいな」程度のソフトな心理的ニーズだと思いがちだけど、レイン博士に言わせればそれは間違いで、食事や睡眠と同じ「ハード」な生物学的要件なんだ、と。本ブログやニュースレター等でも人間関係の重要性はさんざんお伝えしてますけど、もう一回認識改めておこうぜ!ってな位置づけの本ですね。
▼ 参考
- 🤝『Give & Take』のその先へ:与える人が勝つ時代【2025年版】
- 最高の人間関係を構築する7つの柱
- (良くも悪くも)人間関係を大きく左右する【ユーモア】を学んでおこうぜ!
- 【人生100年時代の人間関係】20代と30代では最適な「人脈づくり」は違うらしい|ロチェスター大学長期研究より
- 【失われた友情】断絶した世界でつながりを再発見する13の手法|恋愛にも応用可
- いい友達、悪い友達~1800人に聞いて分かった「親友の条件」トップ10
個人的に面白かったのは、博士が「孤独」を単なる感情ではなく、物理的な「脳の損傷」や「免疫システムの暴走」として扱っている点。提示されるデータが辛辣で、読後は「あ、誰かと喋らなきゃ死ぬわこれ」って真顔になる人も少なくないだろうなーという印象でしたね。
ということで、いつも通りこの本から勉強になったところをまとめておきます。
- 孤独は生物学的な「緊急事態」である:レイン博士によれば、脳は「ひとりぼっち」を「中立的な状態」とは認識せず、「脅威(Threat)」として処理する。古代において孤立は「死」を意味したため、脳はHPA軸(ストレス反応システム)をフル稼働させ、コルチゾールをドバドバ出し、全身に炎症を起こして「敵」に備える。つまり、孤独な人は24時間ずっと「戦場」にいるのと同じ身体状態になっており、これが心臓病や認知症のリスクを爆上げさせている。具体的な数字で言うと、本書で提示されているデータによれば、65歳以上の孤独な男性は死亡リスクが78%も高いそうで、これは喫煙や肥満のリスクを軽く超えている
- 脳の「使わなければ失う」原則:筋トレと同じで、使わない脳の回路は物理的に消滅(プルーニング)する。特に恐ろしいのが「会話」の欠如で、リアルタイムの会話という複雑な処理をしなくなると、言語中枢や記憶領域が萎縮し始める。実際、孤立した認知症患者は、人とのつながりのある患者に比べて2倍の速さで記憶が減退するというデータが提示されている。「人見知りだからひとりでいいや」と思っていても、脳のハードウェア自体が物理的に劣化してしまう
- 鎮痛剤を飲むと「薄情な人間」になる?:(これが個人的に一番衝撃だったんですが、)アセトアミノフェン(タイレノールとかに含まれるやつ)みたいな一般的な鎮痛剤を飲むと、なんと「共感力」が下がるという研究があるらしい。なぜかと言うと、脳内では「体の痛みを感じる場所(前帯状皮質など)」と「他人の痛みを感じる場所」が重複しているから。薬で自分の痛みを麻痺させると、副作用として「他人の痛みを感じる能力(神経的共鳴)」までブロックされてしまう。現代社会が不寛容になってる理由の一つに、鎮痛剤の乱用があるんじゃないか?という示唆は、かなり背筋が凍る話
- 「ボトックス注射」も共感力を下げる:これも似た話で、私たちは相手の表情を無意識に微細に模倣(ミミック)することで、相手の感情を自分の脳内でシミュレーションしている。ところが、ボトックスで顔の筋肉を固めてしまうと、この模倣ができなくなり、相手の感情が読み取れなくなる。美容のためにシワを取ったら、人間関係の解像度まで落ちてしまうというのは皮肉な話。。。
- デジタル・コミュニケーションは「ジャンクフード」:著者は現代のSNSやZoomを「社会的ジャンクフード」と呼んでいる。テキストや「いいね」は、脳にドーパミン(期待)を与えるけど、オキシトシン(満足・安心)は与えてくれない。これは「栄養のないカロリー」を摂取し続けている状態で、結果として「社会的飢餓」が悪化する。特にZoomなどのビデオ通話は、微細な遅延や視線のズレが脳の「予測システム」にエラーを起こさせ続けるため、対面よりも圧倒的に脳のリソースを消費する(これがZoom疲れの正体なのでは?と)
- 私たちは「社交の楽しさ」を見誤る:人間の脳は、社会的リスク(恥をかく、拒絶される)を過大評価するようにできているため、「知らない人と話すなんてダルいし怖い」と予測しがち。しかし実際の実験では、バリスタと少し雑談したり、隣人に挨拶したりする「マイクロ・インタラクション」を行うと、本人が予想した以上に幸福度が上がり、認知機能も改善することがわかっている。つまり、私たちの直感(ひとりでいたい)は、生存本能のエラーであり、意識的に「アンラーニング(学習棄却)」して修正していく必要がある
本書を読んで改めて思ったのは、現代社会が美徳としている「個人の自立」とか「ひとりで生きていく力」みたいなものが、生物学的にはいかに不自然で、脳に負荷をかける行為かということ。
レイン博士は占星術のメタファー(第11ハウスとか土星とか)を持ち出してきたりして、科学者にしては随分とロマンチックな語り口だなぁと最初は思ったんですが、読み進めるとそれが腑に落ちるような感覚があったののも面白かったですね。要は、科学的に突き詰めれば突き詰めるほど、「人間は単体では完成しないデバイスである」という結論にならざるを得ないんですよね。
特に「ソーシャル・ダイエット(社会的食事)」という概念は、我々現代人にとって必須のフレームワークになる気がしています。私たちは食事の栄養素(タンパク質や脂質)にはうるさいのに、社会的栄養素に関しては無頓着すぎる。「今日は誰とも目を合わせて話してないから、脳が栄養失調だな」みたいに、客観的に自分の状態をモニタリングする習慣が必要なんでしょう。
もしあなたが「自分は内向的だから」と思って人付き合いを避けているなら(私自身耳の痛い話ですが)、それは生まれつきの性格ではなく、単に「ジャンクなデジタル交流」で腹を満たして胸焼けしているだけかもしれません。まずはスマホを置いて、コンビニの店員さんに「ありがとう」と言うところから、脳のリハビリを始めてみるのもありでしょうな。
結局のところ、感情を制するのも、キャリアを制するのも、最終的には「誰かと物理的に同じ空間にいる」という、超アナログな行為に集約されるのかもしれないなーなんてかんじたりしましたね(学術的なイノベーションの領域では賛否両論あるのは存じ上げてますけども)。